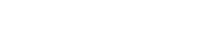「音」とは
音には、高さ、強さ、長さ、音色の4つの性質があります。
- 高さ:1秒間における空気の振動(周波数/Hz)の多少
- 強さ:振動する幅の大小
- 長さ:振動している時間の長短
- 音色:振動する状態の違い
音の基準はA、つまりラの音で440Hzです。
音の基準は1939年にロンドンで行われた国際会議で決められました。ただしヨーロッパ、特にドイツ圏では高いピッチが好まれるため、444〜445Hzが基準だとされています。
日本では、オーケストラや演奏会用のピアノは442〜443Hz、学校や家庭用ピアノ、電子楽器など多くの楽器は440Hzが一般的です(ここ数年のポピュラー音楽は441Hzで作られている曲も多いです)。
ちなみにこの440Hz、ラの音は生まれて一番最初に発する音、つまり赤ちゃんの泣き声に近いと言われており、時報もこの440Hzを使用しています。
音楽の三要素
①リズム(律動)
リズムとは、音の長短、強弱を順次いくつか並べたものです。「ビート(拍)」と「テンポ(速度)」によって決まり、三要素の中で最も音楽の根本を成しているもので、音楽を特徴付けるものです。メロディーやハーモニーのない音楽は存在しますが、リズムのない音楽は存在しません。
②メロディー(旋律)
さまざまな高さ、長さの音がリズムを作りながら構成されていくものがメロディーです。メロディー自体にリズムを持っているので、リズムのないメロディーは存在しません。
③ハーモニー(和声)
ハーモニーとは、ふたつ以上の音が同時に鳴っている時に生まれる音の響き、また音の調和をとることを指します。メロディーが輪郭ならハーモニーは色にあたるので、ハーモニーのつけ方によってメロディーの聴こえ方も変わります。